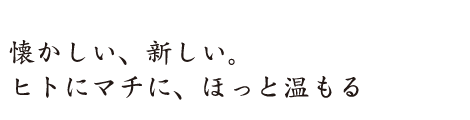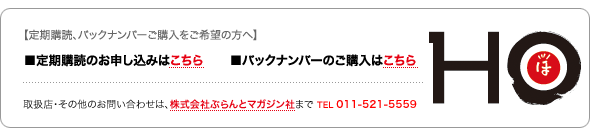「ごろん」で温泉旅行をしてくださった、
HBCパーソナリティ、奥田ゆかさんから、
心のこもった、あたたかいお手紙をいただきました。
文面には、「また、ご一緒に仕事したいですね」なんて書いてあり、
とてもとても嬉しかったです。
はい。
海でも山でも湖でも、どこだって お連れする気満々ですよ!
私もぜひ、またご一緒に仕事したいです!
どうも、ありがとうございます。
奥田ゆかさんがパーソナリティを務める
「ミュージックナイター フルカウント!」
木曜日版は、19時から2時間、HBCラジオで放送中です。
ぜひ、みなさんどうぞ。
リクエストも ばしばししてください。
こういう手紙が来ると、ほんと また 頑張る気持ちがわいてきます。
これからも、一生懸命頑張りますので、どうぞHOをよろしくね。
(みさと)
|
1月25日発売予定の「HO」編集作業着々と進んでいます。
ばりばりと仕事をしている同僚のみんなを横目でちらちら見つつ、自分の机に座って取材時の写真やメモを身ながらあーでもないこーでもないと原稿を書きあぐねていると、なんとなく、どこか行き先を決めずに旅に出たくなるような気がしてきます。
そういえば1カ月ほど前のある朝、会社そばの川がなんだか騒々しかったことがありました。野次馬根性丸出しでのぞきに行くと、なんと「川で泳いでいる人がいる」とのことで、川岸には救急車やら警察やらテレビカメラやら。いくら今年は雪が少ないとはいえ12月の朝、吐く息は白く立っているだけでも足下から冷えが上ってくるような寒さでした。
あの日泳いじゃった人って、どんな人だったんだろう、今の私と同じ気分だったのかなあ…。
いっそ私も泳いでみたらいいアイデアが浮かぶかな?
いや待て、冷えって万病の元なんだっけ、それより温泉のほうが脳が活性化されるか?
…んなこと考えてるヒマに仕事せいよというジョーシの怒号が飛んでくる前に、仕事に戻ることに致しますです、はい。
(写真はカメラマンY氏提供)
(ひろみ)
|
クリスマス。
いつもどおりに仕事をしていると「お手紙でーす」と1通の封筒が届けられました。
なにやら固い感触。
ドキドキしながら開封すると……。
なんとクリスマスカードです!
今発売の号でお世話になった、江部乙温泉の石井支配人からでした。
あたたかいデザインとメッセージに、ココロも身体もほんわか。
思えば、温泉クーポン&パスポートでお世話になっている方々にも、
毎回心温まる言葉をくださる方がいます。
うれしくて、思わず社内の人に見せびらかし…こほん。見てもらい、幸せを共有しております。
こうした幸せをパワーに、楽しい本を作れるよう頑張りたいです。
(しずか)
|
「HOはどんな雑誌ですか?」とよく聞かれます。
広告担当部署もクライアントに説明しにくいとぼやいています。
確かに、観光情報誌ではないし、生活情報誌とも言えません。
取り上げるテーマも桜や紅葉、庭、市場、温泉、ラーメン、カフェとバラバラ。
でも共通しているのは、それぞれの分野で懸命に生きている人たちを一人でも多く登場させようということなのです。
武骨で不器用、でも自分のスタイルを持っている。素敵ですよね。その意味ではHOは「人間情報誌」ということなのかも知れません。
(お) |
HOのタイトルロゴは、最初のプランではひらがなの「ほ。」でした。
つまり、「ほっかいどう」をフィールドにすること、「ほっ」とする話題を集め、「ほんもの」を育てるお手伝いをする。そんな願いを込めて「ほ。」としたかったのです。
ところが、実際にデザインに落とし込む段階になって、デザイナーから「ほ。」ではどうにもバランスが悪い、との意見がでました。
最終的にアルファベットのHOに落ち着いたのですが、ある時、印刷会社の担当者から「これって、大鹿さんのイニシャルですよね」と指摘されてハタと気がつきました。
大鹿寛、HO。
そうだったんだ。でも、偶然はさらに続きがありました。デザイナーの小笠原さんの会社が「HIT&RUN」。「HIT&RUN小笠原」、つまりHOだったのです。
(お) |
![HO [ほ]](../img/logo.gif)